

開催日時 平成22年12月22日(水) 17:45〜
開催場所 1F介護者教室
発表演題 ①ヘルパーステーション・・・高カロリー栄養食の活用法〜より多く摂取するために〜
②特養ホーム2F ・・・オムツ0をめざして〜水分摂って元気はつらつ〜
③特養ホーム3F ・・・オムツゼロをめざして〜水分摂取、歩行訓練の取組みから〜
④デイサービス ・・・機能訓練への意欲を高める為には〜個性と向き合う介護〜
![]()
要約
平成22年春、毎日のように訪問していた利用者さんが徐々に食事が取れなくなってきた。医師からは、高カロリー栄養食を進められるようになったが、口に合わないらしく、それも摂取しないようになった。家族・利用者の立場になり、高カロリー栄養食とはどんなものなのか、どう工夫すれば摂取してもらえるか研究してみた。
その結果、健常者ならば200cc1本は一気に飲めると思われる高カロリー栄養食も、嚥下障害のある高齢利用者の立場に立ってゆっくりと摂取すると、30ccほどの摂取で満腹感を感じてしまうそうだ。また見た目や食感、味、香りなどもゆっくり味わってしまうと嫌に感じてしまうようである。
職員は高カロリー栄養食を、どう食べやすく加工できるか、実際に試行する必要があり、また試行した結果、その情報を家族や利用者さんに提供する事が必要であるとのことである。



![]()
要約
竹内孝仁先生の介護力向上委員会に参加したことで、水分摂取と歩行・起立訓練はオムツを外す事に重要であるという事を学んだ。
利用者の重度化・高齢化がすすむ事に伴い、ADL・QOLの低下も進んでいる実情は、2F特養も同様で、入所者の約3割がオムツを使用している。
この講習会から学んだ事を現場で実際に取り組む事で、ふれもり2F特養も“オムツ0”に向かって行けるのか、その取組みを行った。
その結果、利用者によっては1500mlの水分摂取に制限が掛った利用者もいたが、“オムツ0”に向かって有効にこのプロジェクトが成功に至ったまたは効果が出始めている利用者が徐々に見受けられたとのこと。またこのプロジェクト自体が、職員間(他職種との連携)のチームワークをアップさせるアイテムとなる効果も現れたことで、今後も継続して行きたいとのことでした。



![]()
要約
竹内理論によると「健康な体を維持する為には水分を1500ml以上の摂取が必要」といわれ、水分を多く摂取する事が、意識レベルの向上と循環機能、脳細胞代謝の正常化に繋がり、更に便意・尿意に対し抑制力がかかり、トイレ排泄が可能となるのである。
より健全な生活リズムを提供する事が、利用者のADL向上・介護者の認知症理解、そしてBPSDの軽減を目的に、竹内理論に基づいた取組みをおこなった結果を報告する。
取組み当初、これまでの倍近い、1500mlの水分を提供する事に対し職員には疑問の声が聞かれた。そのため、水分の必要性とその効果について職員の理解を深める事からスタートした。また利用者には個々の嗜好を考慮しながら、工夫する事で1日1500mlの水分摂取をクリアーしていった。
その結果、尿混濁や皮膚の落屑など眼に見える効果があったほか、トイレでの座位排便や歩行能力の促進・歩行距離の延長などの効果がではじめるなどADL・QOLの向上につながる効果が得られた。
また施設介護にみられがちな思い込みの介助法の改善にもつながり、今後も継続意していきたくなる結果となった。



![]()
要約
身体機能面の低下は家族の介護負担の増大を招き、結果高齢者は長年住みなれた自宅での生活の場を失うきっかけとなってしまう。その為身体機能面へのアプローチは、デイサービスでは重要なサービスといえる。しかし利用者は職員に促されるまま、機能訓練メニューは職員が当該利用者に適当と思われる訓練を選定するなど、自立支援にそぐわない状況下であった。
そこで、現在提供している機能訓練が、利用者が自発的に参加できる魅力(活力)あるものとして提供できないか試みた。
方法として立山登山をイメージしたチャレンジシートを用意し、眼に見える形の成果と目標を表す事とした。また認知症利用者に対しては、個別に機能訓練を行うことにした。更に機能訓練に対するアンケート調査も実施した。
アンケート調査では“歩く訓練はしたくないが、自立した在宅生活を送る為には歩行訓練は必要である”と考えている事が分かった。また実施した結果立山登山の楽しみが利用者の参加意識を高め、意欲的に訓練に参加できることが見て取れた。認知利用者の場合も、声掛けの量が増えるため、身体的な効果以外に精神面における効果も見て取れた。


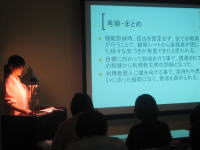
![]()
◆演題が全て終了後、それぞれの発表に対し講評をいただきました。
=講評=
①ヘルパーステーション 坪本介護主任(不在の為、有島介護主任が事前に預かっていた講評を代読)
②特養ホーム2F 鷲塚看護師・ケアマネ
③特養ホーム3F 尾崎看介護部長
④デイサービス 有島介護主任
=総評=
■浜崎施設長・・・投票の結果、施設長から富山県老師協大会にて発表する演題が、デイサービスの
『機能訓練への意欲を高める為には〜個性と向き合う介護〜』に決定した事が報告されました。




